四月頃の暖かさや真冬の寒さの繰り返し天候の変化が激しい
それでも時期にはちゃんと芽が出たり花が咲いてきました
晴天の日の出だったのでカメラを持って家の周りをウロウロ!
高い木の枝から落ちる小さな雪が落ちながら次々と他の枝を
震わせ ますます大きな粉柱になり朝日に照らされて輝きました
初めて伺ったEBIさん宅の玄関で先ず強力な出迎えが一対のシーサー?
それにギョッ!として目線を庭に向けたら見たら信楽地方から来られた
裕福そうなタヌキが「タマ」をひこずっている、もう少し目線を落とすと
未だ寒い時期だけど冬眠しないカエルが三匹、
睨まれたり見せびらかされたりでカエルにかえれず写してしまった
今回は家の建設予定地に生えている大きな松を伐採します、この山には三つ葉ツツジやガマズミその他のお気に入りの木が
かなり生えているので何とか残したく通常ではやらない伐り方で、切り倒した木を地面まで倒さずに隣の木に立てかけるように
(かかり木という)方向を良く見て切り口を入れます、写真では二本の松を栗の木に倒し下側から少しずつ切って降ろします、
これはけっこう危険な方法で切っていくうちにバランスが崩れて反対方向に倒れる事もあります
枯れ松が雪などで倒れ空中で止まっている事もありちょっと厄介
今年は何時までもスタッドレスタイヤが外せん、もちろん畑の準備などサッパリ ホウレン草の育ちが遅いもんでビニールトンネルを
見たら数箇所の穴開き状態たぶんヒヨドリやツグミが野菜を食べようとしてつつき破った(見とらんけどたぶん いいや絶対そうじゃ!
なに!? ワシがボロのビニールを使おた? なにおバカな事を言うてくれる そんな事ありゃぁせんワシ無実じゃ!)かな
中の暖かい空気が抜けるように「よぉーし やるどぉー」の気持もぷゎ~と抜けてしまう やれやれ・・・
地域の行事で広島市内のスーパー銭湯へ、塩、電気、気泡、打たせ、等などに梯子してすっかりほてったところで食事
今まであまり見たことがかった演劇鑑賞、初めのうはこんな芝居とか思っていたけど涙が出ていた、場内が明るくなって
同行した団塊世代のオッサン達も「ワシゃぁ涙が出たよ」とか「暗い時に拭いた」と言っていた、やれやれ皆似たようなもんかぁ
今日は一日中 東広島方面で走り回る、先ずは若い夫婦が福富町で自然農法をスタートされその農業用水確保の相談を受けて
以前やっていた地質調査と井戸屋さんに変身、現地を見ながらアドバイス、お礼に努力の結晶であるニンジン、ゴボウ、
チンゲン菜を頂く心して味わうかな、
そして私の勧め 本人決定で I ターン定住され同じく自然農法を始めたそれほどは若くない友人宅に様子伺い、「あまり頑張り
過ぎないように」と声がけ、
三箇所目はこれも25年来の友人で、うちで栽培した自然農法米(ミルキークイーン)を届けて犬のお相手でひとしきり遊んだ後は
香辛料が爽やかな昼食とデザートで大満足、帰りには庭木の剪定を頼まれる、今年も忙しくなるのお。
雪で外作業はできず部屋でパソコンをやっていたら
ストーブの調子がいまいち、ジープの車庫で分解
最近のストーブはコストダウンのためか素人には
触らせないためかバラしにくい
前回のメンテナンス時にはやっていなかったストーブの
心臓部分である燃料ノズルを外して見たらなんと
カーボンがこびり付いていた、特にノズルの先端部分
は傷付けないよう慎重に掃除、おかげで今はバッチリ!
「百姓は冬の間なんにもすることが無いじゃろ」とよく言われるけど
「それはちがうでぇ」と思う、一般農業はそうかもしれんが
百姓は百のやる事が・・・・ まぁ自分で用事を作っておるけどのお
フライトにそなえて先日バッテリー充電、西飛行場まで航空燃料も取りに行き
給油OK機体の掃除もバッチリあとは当日飛ぶだけ、家から格納庫まで約20
kmをオープンのジープで移動、さすがに1月こりゃぁさぶい
機体を格納庫から引き出し離陸地点に移動、ここでの守って欲しい安全事項を
説明、特に大勢の人が来ると予測もしない動きがあるのでかなりしつこく説明
しながらOILチェック、燃料再確認、機体の外周を点検しながら回り「じゃぁ機内
へどうぞ!」と今度は中での説明も一通り終り いよいよエンジンスタートの手順
周囲の安全確認OK、マスタースイッチ→ON、アンチコリジョンライト→ON、
ミクスチャー→フルリッチ、キャブヒート→OFF、イグニッション→・・・・・・・・ ??
ありゃ?・・・ そういやぁ今朝はマイナス5度じゃった、しもおたぁ~さっきまでは
順調しかし、なんでも思い通りにいかんのがおもしろい、ジープのバッテリーを
繋いで回った 飛んだら気が緩んでしまいオヤジギャグの連発 やれやれ!
五右衛門風呂の体験入浴したいとの事でわたしの特徴でもある心遣いで順調に取材が進むようにと
気を利かせて丁度ええ湯加減に沸かしておいたら、「火を焚くところも撮影したい」となり焚くことに
日も落ちてきたので皆んな早く終わらせなくてはとの空気、脱衣場は物置の中、そこで脱いで
冷え切ったコンクリートの洗い場へ、その間にもお湯はどんどん上昇そんな時、レポーター(ナベさん)
にはいろいろと撮影指示か飛ぶ勿論映すために窓は全開(さぶぅ)、いざ入ろうと片方の足先を湯に
用心してゆっくりと入れた、入れるのはゆっくりだが「あちぃ!!」が聴こえた瞬間お湯から離れて
いた、アノ歳にしてはなかなか俊敏さすが元プロ野球の選手、大変なのは入ったレポーターだけで
後は皆笑って眺めている(ほんとに気の毒)、風呂場とはいうだけでまるで寒空原野で煮えたぎる
露天風呂、いくら熱くてもカメラの前、片手は常にタオルで前を隠し口を尖らせ首に力をいれただ我慢の
時間、水を入れながらなんとか腰まで沈む、へそから下はゆでだこに上は冷凍庫の中、これがプロの
心意気!ゴリッパ!
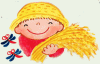































































コメント