子供の頃には夏の夕暮れ時から台所のすだれに飛んできて「スィ~~ッチョン!スィ~~ッチョン!」と聞かせてくれくれました、名前が分からなかったので「スィッチョンが来とるでぇ!」と、今でも分からないけど自分では‘スィッチョン’です
葛は‘カズラ’といっていました、小学生の頃アキちゃん(直ぐ上の兄)と「かずらの根からデンプンが取れるらしいからやってみようかぁ」と云うことになり家の近くにあった防空壕の穴の横あたりで掘りまくって60cm~80cm位のを3本か4本ゲット、持ち帰って押切機で輪切りにしたものを金タライの中でハンマーで叩く水を入れて揉みしぼり放置すると白くて指で押すと‘ギュッギュッ’と音がしていた、乾かした物を茶碗の中で砂糖とお湯を入れてこね回し後は食べるだけ、子供の頃から食い意地が張っていたんですねぇ
自然農法栽培では農薬や化学肥料を使用しないので虫や病気を完全に止めるのはなかなかです
最初はすりおろしニンニクと唐辛子の粉末を水に溶かして散布していたけどカメムシの飛来が多くて効果が確認できなかった
物理的に排除しょうとバケツの中に落としたとたんヴゥワーっと這い出て手に登ってきた、それならとバケツの底に水を入れてみた入れないよりはましだけどやはり這い出る
子供の頃(50年以上前)ハエや蚊には手押しスプレーに石油(灯油)の様なものを入れてシューシューやっていたのを思い出しペットボトルのキャップ3杯入れてみました、油類は水面に浮かぶので多く入れる必要はないでしょう
ポイントはカメムシの下に水と灯油の入ったバケツを置いてふるい落としますほとんどは動かなくなるけど時々バケツを動かすとほぼ全滅、とても簡単ですどーぞ!。
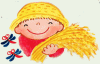




































コメント