広島市内の黄金山近くにあるGOSさん宅で新年会、明日はかなり強い寒波の予報なので水道の凍結対策をしてから移動
私の好物がズラッとお膳に、メインの「しょっつる鍋」は子持ちなどのとても新鮮なハタハタが準備されていた
|
|||||
|
ビニールハウスで作った物置は入口が弱いので、積雪で潰れないように、突風で捻じ曲げられないようにと補強 ポイントは足場単管 丁寧にやりたい場合には  TAMさんもゆとりの様子(暇なだけかも)
焼芋を買いに来た方に「焼芋の重さをピタリと当てたらプレゼントしますよ!」と、そんなにゃぁ当たらんだろうと思っていたら
3組がピタリと当りタダで焼きたてをゲット! タダでゲットした人「やったぁ! 良かったァ!」 私ゃ「ありゃぁ~残念!」
出店しているといろいろな方達が訪ねてこられます ティムさんは今日も元気いっぱい
舞台では、メープルカイザーや恒例となっているレイフラワーハッピーのメンバーがフラダンスを披露 里山まなぶ会の初仕事、昨年までやっていた山の大きな枯れ桧を伐倒した 食事は、丸太ストーブを使いながらすすめる、着火して間もない頃に鍋などを直接載せると火が消えそうになるので木片であいだを開ける 今日は、午前も午後もかなり危険を伴う作業だったので写真を写す暇がなっかった 数年ぶりにTAKEさんが来訪、「仔猿を連れてきたよ」「何処に?」「車ん中」で、行ってみた うちの刈払機は45cc、【コザル】は35cc、ヘッドライトやウインカーな等すべてOK、ホンダモンキーよりもはるかに小さい 最初は、足がペダルまで上がらない、ポストの屋根を片手で持って足上げの練習、ブレーキの効かせ方などを聞いてスタート |
|||||
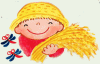










































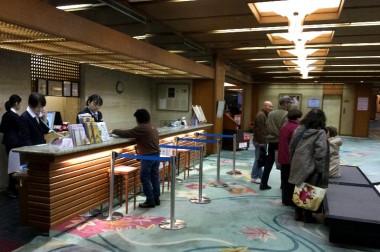





















コメント